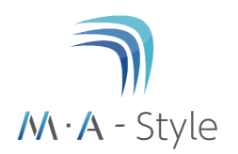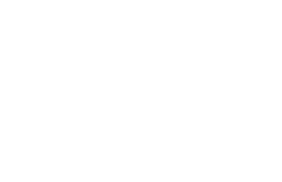てんかんの治療は長期にわたることがあり、医療費の負担が心配になる方もいらっしゃるでしょう。
日本には、こうした経済的な負担を軽減するための様々な公的制度があります。
今回は、てんかん治療でまず頼りになる公的医療保険制度と、その上で民間の医療保険がどのような役割を果たすのか、そして加入時の注意点について解説します。
てんかん治療でまず活用できる「公的医療保険制度」
日本の公的医療保険(健康保険など)は、てんかん治療における経済的負担を支える基本となります。
治療費の自己負担を軽減する「健康保険」
医療機関での診察、検査、薬の処方、入院など、医師が必要と認めた治療の多くが保険適用となり、窓口での自己負担は原則1~3割に抑えられます。
ただし、保険適用外の治療(自由診療)などを選択した場合は、全額が自己負担となる点に注意が必要です。
自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」
治療が長期化したり、手術などで医療費が高額になったりした場合でも、1ヶ月の医療費の自己負担額には所得に応じた上限が設けられています。この上限を超えた分は、申請により払い戻されるのが「高額療養費制度」です。
【申請先】: ご自身が加入している公的医療保険の保険者(会社の健康保険組合、協会けんぽ、お住まいの市区町村など)に申請します。
休業中の生活を支える「傷病手当金」
てんかんの発作などにより仕事を休まざるを得なくなった場合、生活を支えるための制度です。
【対象者】: 主に会社員や公務員などが加入する健康保険の被保険者が対象です(国民健康保険には原則としてこの制度はありません)。
【内容】: 連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降、最長1年6ヶ月間、給与のおよそ3分の2が支給されます。
【申請先】: ご自身が加入している健康保険の保険者に、医師の証明などを添えて申請します。

民間の医療保険の役割と加入時の注意点【重要】
民間の医療保険は、公的医療保険でカバーしきれない費用を補うためのものです。
民間医療保険で備えられる費用
・高額療養費制度を使っても残る自己負担分
・入院時の差額ベッド代や食事代の一部
・先進医療の技術料
・通院のための交通費 など
【最重要】てんかんと診断された後の新規加入について
民間の医療保険に新規で加入する際は、現在の健康状態や過去の病歴を正しく申告する「告知義務」があります。
てんかんは、この告知義務の対象となる病気です。
そのため、てんかんと診断された後に、一般の医療保険や死亡保険に新規で加入することは、非常に難しくなるか、加入できても「てんかんおよびその合併症は保障の対象外」といった特別な条件が付くのが一般的です。
「てんかん治療に特化した保険」というものは、基本的に存在しないと考えるのが現実的です。
診断前に加入していた保険は確認を
もし、てんかんと診断される前に民間の医療保険に加入していた場合は、その契約内容に基づいて、入院給付金や手術給付金などを受け取れる可能性があります。
ご自身の契約内容を改めて確認してみましょう。
引受基準緩和型保険という選択肢
告知項目を少なくし、加入条件を緩やかにした「引受基準緩和型保険」であれば、てんかんの治療状況によっては加入できる可能性があります。
ただし、保険料が割高であったり、加入後一定期間は保障額が削減されたりするといった注意点があります。

まとめ
てんかんの治療にかかる経済的負担に対しては、まず、健康保険や高額療яв費制度、傷病手当金(対象者の場合)といった公的制度が大きな支えとなります。
ご自身が利用できる制度を正しく理解し、活用することが重要です。
その上で、民間の医療保険は、自己負担分などを補う役割を果たしますが、てんかんと診断された後の新規加入には高いハードルがあることを認識しておく必要があります。
もしもの備えを検討する際は、こうした点も踏まえ、ご自身の状況に合わせて慎重に判断しましょう。不明な点は、各制度の窓口や専門家に相談することをお勧めします。