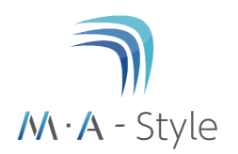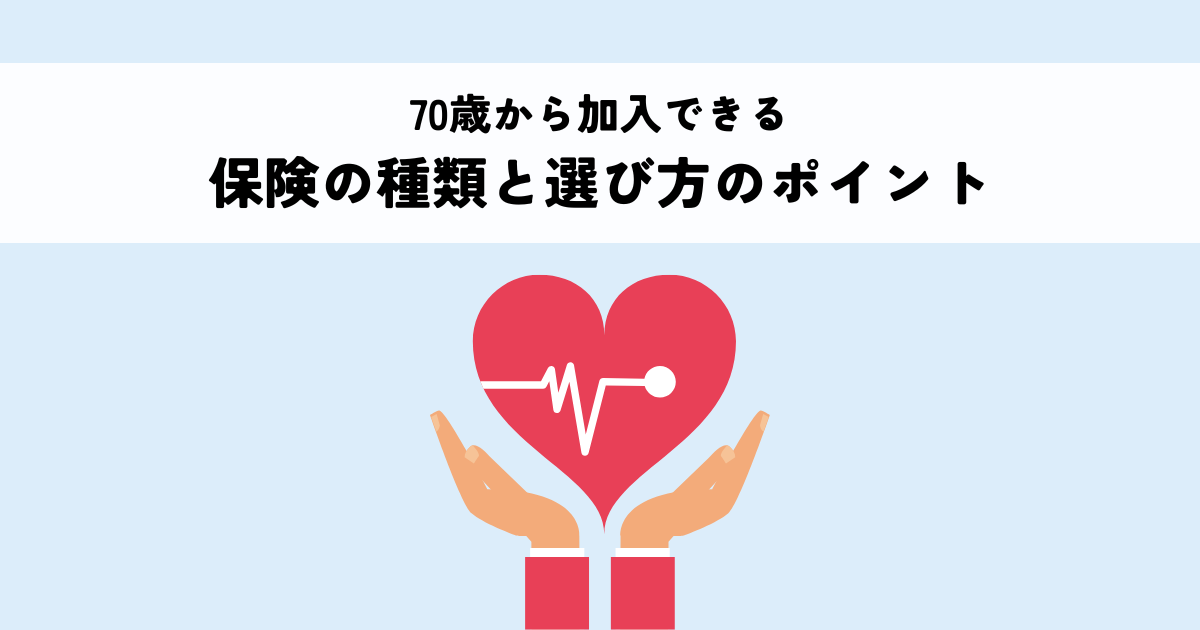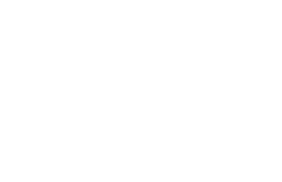70歳を迎え、将来の健康や介護への備えとして、保険への加入を検討される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、70代からの保険選びは、若い頃とは大きく異なります。まず、私たちの生活を支える手厚い公的制度を正しく理解することが、何よりも重要です。
この記事では、70代の方を支える公的制度を解説し、その上で民間の保険がどのような役割を果たすのか、そして選ぶ際の注意点について解説します。
70歳からの暮らしを支える「公的制度」をまず理解しよう
民間の保険を検討する前に、70代の医療や介護を支える2つの重要な公的制度を確認しましょう。
医療費の自己負担が軽くなる「後期高齢者医療制度」
75歳(一定の障害がある方は65歳)以上になると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」に移行します。
これにより、医療機関の窓口での自己負担割合は、原則1割(現役並み所得者は2割または3割)になります。
また、1ヶ月の医療費の自己負担額には上限が設けられており、上限を超えた分は払い戻される「高額療養費制度」も利用できるため、医療費の負担は大幅に軽減されます。
介護が必要になった時の「公的介護保険制度」
40歳以上の国民が加入している制度で、市区町村から要支援・要介護認定を受けると、ヘルパーの派遣やデイサービス、施設への入所などの介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。
介護にかかる経済的な負担を社会全体で支える仕組みです。
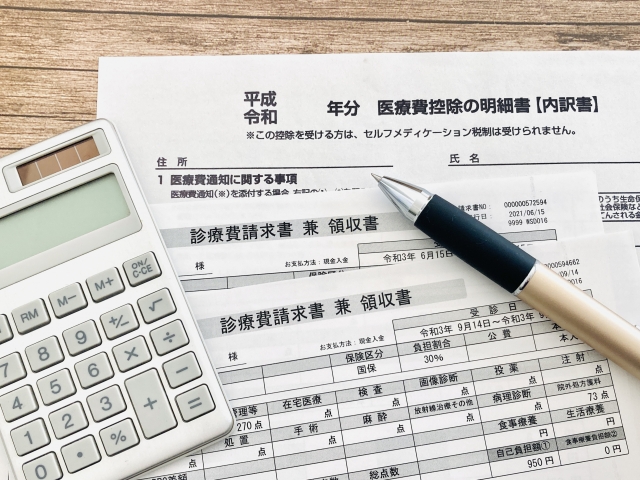
公的制度を補う「民間の保険」の役割と種類
民間の保険は、これらの手厚い公的制度を利用してもなお発生する自己負担分や、公的制度の対象外となる費用に備えるためのものです。
70歳から加入を検討できる主な選択肢は以下の通りです。
主な選択肢は「引受基準緩和型」や「無選択型」の保険
70歳以上の方が新規で保険に加入する場合、健康状態に関する告知のハードルが高くなるため、告知項目を少なくして加入しやすくした「引受基準緩和型保険」や、告知が不要な「無選択型保険」が主な選択肢となります。
【注意点】
保険料は一般の保険に比べてかなり割高に設定されています。
加入後一定期間(1年など)は、受け取れる給付金が半額に削減されるなどの保障の制約があるのが一般的です。
1. 引受基準緩和型の医療保険
入院や手術をした際の、高額療養費制度を使っても残る自己負担分や、差額ベッド代などに備えるための保険です。
2. 引受基準緩和型の介護保険
公的な介護保険サービスを利用した際の自己負担分や、制度の対象外となるサービス(消耗品費、食費など)の費用に備えるため、要介護状態になった際に一時金や年金を受け取れる保険です。
3. 少額短期保険(ミニ保険)
死亡時に葬儀費用などに充てるための少額の死亡保障や、ケガによる入院・手術に備える傷害保険など、保障をシンプルにすることで保険料を抑え、高齢でも加入しやすい商品があります。

70歳からの保険選びで注意すべき点
本当に民間保険が必要か、冷静に検討する
まずは、日本の手厚い公的制度でどのくらいカバーされるのかを理解しましょう。
その上で、ご自身の貯蓄額と照らし合わせ、それでも不足すると感じる部分があるか、そのために割高な保険料を払ってでも民間の保険で備える必要があるかを冷静に判断することが最も重要です。
保障内容をしっかり確認する
加入を検討する際は、どのような場合にいくら給付金が支払われるのか、そしてどのような場合は支払われないのか(免責事由)をしっかり確認しましょう。
特に引受基準緩和型保険の保障削減期間には注意が必要です。
保険料の支払い能力を考える
高齢期の保険料負担は、家計に大きな影響を与えます。
年金収入などを考慮し、無理なく支払いを続けられるかを慎重に検討しましょう。
保険料を一括で支払う方法もありますが、まとまった資金が必要になります。
まとめ
70歳からの備えを考える際、まず頼りになるのは「後期高齢者医療制度」や「公的介護保険制度」といった国の手厚いセーフティネットです。
これらの制度でカバーされる範囲を正しく理解することが第一歩です。
その上で、不足する部分にどうしても備えたい場合に、民間の保険が選択肢となります。
ただし、70歳からの加入は、保険料が割高になるなどの注意点も多いため、本当に必要かどうかをご自身の貯蓄状況やライフプランと照らし合わせて慎重に判断することが大切です。
もし検討する際は、保険会社や相談窓口で詳しい説明を聞くのも一つの方法です。