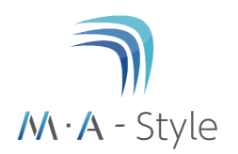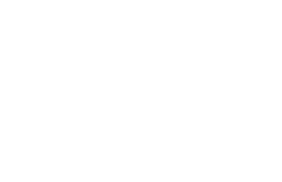介護保険と医療保険は、高齢者や病気、けがを抱える人々の生活を支える重要な保険制度です。
しかし、それぞれ目的や適用範囲に違いがあります。
この記事では、介護保険と医療保険の違い、優先順位、併用できるケース、注意点について解説します。
それぞれの保険制度を理解することで、より適切な選択と活用ができるようになるでしょう。
医療保険と介護保険の違い
対象者の違いを解説
医療保険は、日本国内に住むすべての国民が加入している社会保険制度です。
年齢や職業に関係なく、原則として誰もが医療機関を受診すれば保険が適用されます。
一方、介護保険は原則として40歳以上の人が加入し、要介護認定を受けた場合にサービスを利用できます。
介護保険には年齢による区分があり、65歳以上の方を「第一号被保険者」、40歳から64歳までの方を「第二号被保険者」と呼びます。
第一号被保険者は、介護が必要と判断された場合に介護保険から給付金を受け取ることが可能です。
第二号被保険者は、脳血管疾患や末期がんなどの特定疾病により要介護認定を受けた場合に限り、給付金を受け取ることができます。
サービス内容の比較
医療保険は「治療」を目的としており、病気やけがの診療、手術、薬の処方といった医療行為に適用されます。
風邪や骨折などの急性疾患や、糖尿病などの慢性疾患に対して、通院や入院、投薬などの医療サービスが提供されます。
医療保険は、病気やけがを治すための支援に焦点を当てている点が特徴です。
一方、介護保険は「生活支援・介助」を目的としており、高齢や障がいなどにより日常生活の動作が困難になった人に対し、身体的・精神的な自立を支えるサービスを提供します。
具体的には、訪問介護、デイサービス、福祉用具の貸与、住宅改修などが該当します。
これらのサービスは、医療的な治療ではなく、日常生活の質を維持・向上させることに主眼を置いています。

保険の併用条件と手順
併用の可否と条件
原則として、同一のサービスに対して介護保険と医療保険を併用することはできません。
ただし、サービスの対象部位や目的が異なる場合には、例外的に併用が認められるケースがあります。
例えば、介護保険でリハビリを受けていた人が、新たにがんの治療が必要になった場合、がんの治療には医療保険が適用され、従来のリハビリには介護保険が適用されます。
訪問看護や訪問リハビリテーションについては、原則として要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されます。
ただし、医師の指示による特別な医療行為が必要な場合や、介護保険では対応できない専門的なリハビリが必要な場合には、医療保険が適用されることがあります。
要介護認定のプロセス
介護保険サービスを利用するためには、市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
申請は、本人はもちろん、家族や地域包括支援センターなどに代行してもらうことも可能です。
申請後、市区町村の職員などによる訪問調査が行われ、心身の状態について聞き取りが行われます。
訪問調査の結果や医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査が行われ、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されます。
認定結果は原則として30日以内に通知されます。
介護保険の利用手順
要介護認定の結果に基づき、介護サービスを利用するための計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランは、本人や家族が作成することもできますが、ケアマネジャーに依頼するのが一般的です。
ケアマネジャーは、利用者の状況や希望に応じて、適切なサービスを組み合わせたケアプランを作成し、サービス事業者との調整を行います。
ケアプランに基づき、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用します。
利用者は、かかった費用の一部を自己負担し、残りは介護保険から給付されます。
自己負担割合は、所得に応じて1割、2割、または3割となります。

まとめ
医療保険と介護保険は、対象者やサービス内容が異なるものの、どちらも私たちの生活を支える重要な社会保険制度です。
原則として併用はできませんが、例外的に可能なケースも存在します。
介護保険の利用には要介護認定が必要であり、そのプロセスを理解しておくことが大切です。
それぞれの保険制度を適切に活用し、必要な支援を受けられるようにしましょう。