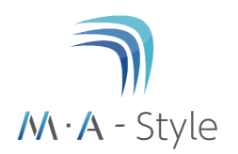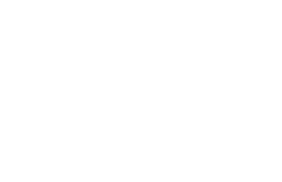椎間板ヘルニアの治療は、症状や治療法によって費用が大きく変動するため、事前に費用の目安を知っておくことは、安心して治療に臨むための重要な準備となります。
今回は、椎間板ヘルニアの治療で利用できる公的医療保険(健康保険)の制度と、ご自身で備える必要がある費用について、具体的なポイントを解説します。
椎間板ヘルニアの治療と公的医療保険の適用
手術と入院費用は保険適用で自己負担は原則3割
椎間板ヘルニアの手術や入院費用は、原則として公的医療保険が適用され、医療費の自己負担はかかった費用の3割(年齢・所得による)となります。
手術の種類や入院期間によって総額は大きく変動しますが、あくまで一般的な一例として、手術と1週間程度の入院で総額100万円程度の医療費がかかった場合、窓口での自己負担額は30万円程度となります。
※注意:これはあくまで概算の例です。
実際の費用は、医療機関、手術・治療の内容、入院日数などによって大きく異なります。
高額療養費制度で自己負担額はさらに抑えられる
高額な医療費がかかった場合でも、1ヶ月の自己負担額には上限が設けられています。
この上限額を超えた分は、申請により払い戻される「高額療養費制度」を利用できます。
自己負担の上限額は年齢や所得によって定められており、経済的な負担を大きく軽減することができます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。
先進医療は全額自己負担になるケースも
近年開発されている高度な医療技術を用いた手術(先進医療)は、公的医療保険の対象外となる場合があります。
その場合、先進医療にかかる技術料は全額自己負担となります。(診察や入院など、通常の治療と共通する部分は保険適用されます)
治療法を選択する際は、その効果やリスクだけでなく、保険適用の範囲についても医師から十分な説明を受けることが重要です。
医師の処方があればコルセットなどの装具も保険適用
医師が必要と判断し、処方したコルセットや装具の購入費用は、療養費として申請すれば、審査後に自己負担分を除いた額が払い戻されます。
ご自身で判断して購入したものは保険適用になりませんので注意が必要です。
治療費の自己負担分や治療中の生活費にどう備えるか 【追加セクション】
公的医療保険は非常に手厚い制度ですが、全ての費用をカバーできるわけではありません。
以下の費用は自己負担となるため、ご自身で備えておく必要があります。
高額療養費制度を使っても残る自己負担分
先進医療にかかる技術料
入院時の差額ベッド代や食事代の一部
治療で仕事を休んでいる間の収入減少
これらの自己負担や収入減少に備える方法として、民間の医療保険や就業不能保険といった選択肢があります。
民間の医療保険に加入していれば、入院日数や手術の種類に応じた給付金を受け取ることができ、自己負担分の支払いに充てることができます。
また、就業不能保険は、病気やケガで長期間働けなくなった際の収入減少をカバーするのに役立ちます。

保険適用を受けるための手続きの基本
手続きの基本的な流れ
公的医療保険の手続きは、国民健康保険でも会社の健康保険でも、基本的な流れは同じです。
医療機関の窓口で保険証を提示して自己負担分を支払い、高額療養費などの申請は、ご自身が加入している保険者(市区町村や健康保険組合など)に対して行います。
申請に必要な主な書類
・保険証
・医療費の領収書
・(高額療養費の場合)申請書 など
領収書は申請に必須ですので、大切に保管しておきましょう。
申請期間は治療日から2年以内
医療費の払い戻しなどの請求権は、原則として診療を受けた日の翌日から2年で時効となります。
治療が終わったら、速やかに手続きを行うことをお勧めします。
高額療養費制度の申請先
申請先は、ご自身が加入している公的医療保険の保険者です。
国民健康保険の場合はお住まいの市区町村役場、会社の健康保険の場合は健康保険組合や協会けんぽなどが窓口となります。

まとめ
今回は、椎間板ヘルニアの治療費について、公的医療保険の適用範囲や手続きを中心に解説しました。
治療費が高額になる場合でも、高額療養費制度などを活用することで自己負担は一定額に抑えられます。
一方で、先進医療の費用や治療中の収入減少など、ご自身で備える必要がある部分もあります。こうしたリスクに対しては、民間の医療保険なども有効な選択肢の一つです。
不明な点があれば主治医やご加入の保険者に確認し、お金の不安を少しでも解消して、安心して治療に専念できるように準備を進めましょう。