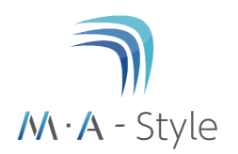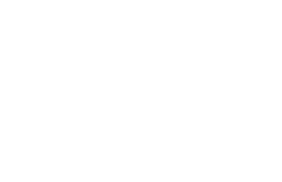うつ病の治療は長期にわたることもあり、医療費の負担が心配になる方も多いでしょう。
治療に専念するためには、経済的な不安を少しでも和らげることが大切です。
日本には、こうした医療費の負担を支えるための様々な公的制度があります。
今回は、うつ病治療でまず活用できる公的制度と、その上で民間の医療保険がどのような役割を果たすのか、そして注意点について解説します。
うつ病治療を支える「公的制度」
まず基本となるのが、日本の手厚い公的制度です。これらを活用することで、医療費の負担を大幅に軽減できます。
1. 健康保険(公的医療保険)
うつ病の診察、カウンセリング(保険適用の場合)、薬の処方など、基本的な治療費は健康保険の適用対象となり、窓口での自己負担は原則1~3割に抑えられます。
2. 自立支援医療(精神通院医療)制度【重要】
うつ病などの精神疾患で通院治療を続ける場合に、医療費の自己負担をさらに軽減できる制度です。
この制度を利用すると、健康保険適用後の自己負担割合が通常3割から原則1割に軽減されます。
また、所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられます。
【申請先】: お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課など)で申請します。
3. 高額療養費制度
入院などで1ヶ月の医療費が高額になった場合に、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される制度です。(自立支援医療制度を利用している場合、そちらが優先されることが多いです)
【申請先】: ご自身が加入している公的医療保険の保険者(会社の健康保険組合、協会けんぽ、市区町村など)に申請します。
4. 傷病手当金
うつ病の治療のために仕事を休み、給与が支払われない場合に、生活を支えるための制度です。
【対象者】: 主に会社員や公務員などが加入する健康保険の被保険者が対象です(国民健康保険には原則としてこの制度はありません)。
【内容】: 連続して3日間休んだ後、4日目以降、最長1年6ヶ月間、給与のおよそ3分の2が支給されます。
【申請先】: ご自身が加入している健康保険の保険者に、医師の証明などを添えて申請します。

民間の医療保険の役割と加入時の注意点
民間の医療保険は、公的制度でカバーしきれない費用を補うためのものです。
診断前に加入していた保険は給付対象の可能性
うつ病と診断される前に民間の医療保険に加入していた場合、その契約内容に基づいて、入院給付金などが受け取れる可能性があります。
ご自身の契約内容を改めて確認してみましょう。
給付金を請求する際は、保険会社所定の請求書、医師の診断書、領収書などが必要となります。
手続きの詳細は、ご加入の保険会社にご確認ください。
【最重要】うつ病と診断された後の新規加入について
民間の医療保険に新規で加入する際は、現在の健康状態や過去の病歴を正しく申告する「告知義務」があります。
うつ病などの精神疾患は、この告知義務の対象となります。
そのため、うつ病と診断された後に、一般の医療保険や死亡保険に新規で加入することは、極めて困難であるのが現実です。
告知項目を少なくした「引受基準緩和型保険」でも、精神疾患の既往歴があると加入できない商品が多くあります。

まとめ
うつ病の治療にかかる経済的負担に対しては、まず、健康保険はもちろん、「自立支援医療制度」や「傷病手当金」(対象者の場合)といった公的制度が大きな支えとなります。
ご自身が利用できる制度を正しく理解し、市区町村の窓口などに相談しながら活用することが重要です。
民間の医療保険は、診断前に加入していた契約があれば力強い支えになりますが、診断後の新規加入は非常に難しいという点を認識しておく必要があります。
この記事が、経済的な不安を少しでも解消し、安心して治療に専念するための一助となれば幸いです。