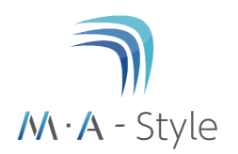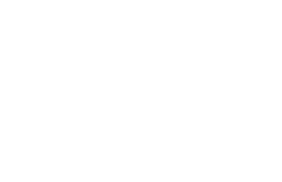生命保険への加入を検討する際、健康状態に関する多くの告知事項に戸惑うことはありませんか。
「どこまで正直に伝えれば良いのか」「このくらいの症状なら伝えなくても大丈夫だろうか」といった不安は尽きないものです。
しかし、告知を正しく行わないと、将来、保険金が受け取れないといった事態につながる可能性もあります。
今回は、安心して保険選びを進めていただくために、生命保険の告知に関する重要なポイントを丁寧に解説します。
生命保険における告知の範囲
告知が必要となる病気
生命保険の告知では、過去にかかった病気や現在治療中の病気について、正確な情報を伝える必要があります。
告知が必要な病気の範囲は保険会社や商品によって異なりますが、一般的に、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病など、生命に影響を与える可能性のある病気が該当します。
また、手術や入院を伴う病気やケガ(例:骨折、ヘルニアなど)も告知の対象となります。
過去に治療が完了している病気であっても、告知を求められる場合がありますので、告知書の質問事項をよく読んで回答することが重要です。
告知が必要となる期間
告知を求められる期間は、多くの場合「過去5年以内」が基準となりますが、保険会社や商品によっては、それ以前の病歴について問われることもあります。
特に、再発の可能性がある病気や、現在も経過観察を続けている病気については、正確な情報を伝えることが大切です。
告知期間に関する不明な点は、保険会社に確認するようにしましょう。
告知が必要となる治療
告知が必要なのは、入院や手術だけではありません。
通院や投薬による治療も含まれます。
また、検査の結果、医師から再検査や治療、経過観察を勧められた場合も告知の対象となります。
治療内容を記入する際は、治療期間、治療方法、服用した薬の名前などをできるだけ正確に記入しましょう。
告知が不要となる可能性のあるケース
すべての病気や治療が告知の対象となるわけではありません。
ごく軽微な風邪やインフルエンザなど、短期間で治癒し後遺症もない病気は、多くの場合、告知は不要です。
また、健康診断で「要精密検査」と指摘されても、精密検査の結果「異常なし」と診断された場合は、告知が不要なこともあります。
ただし、ご自身で判断に迷う場合は、必ず保険会社に問い合わせて確認することが大切です。
告知書はどこまで書くべきか
告知義務違反のリスク
故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知したりすることを「告知義務違反」といいます。
告知義務違反が判明した場合、保険契約が解除されたり、いざという時に保険金や給付金が支払われなかったりする可能性があります。
場合によっては、それまでに支払った保険料が戻ってこないこともあります。
告知は契約における重要な義務ですので、正確に記入することが不可欠です。
告知事項は具体的に記述する
告知事項は、曖昧な表現を避け、具体的かつ詳細に記述する必要があります。
例えば、「胃痛があった」だけでなく、「20XX年X月に胃痛のため〇〇病院を受診。
胃カメラ検査の結果、胃潰瘍と診断され、薬で3ヶ月間治療した」というように、具体的な情報を記載しましょう。
記憶が曖昧な場合は、診療明細書を確認したり、医療機関に問い合わせたりして、正確な情報を確認するよう努めましょう。
告知をスムーズに進めるためのヒント
引受基準緩和型保険(限定告知型保険)という選択肢
持病や既往症がある方向けに、告知項目を少なくして加入しやすくした「引受基準緩和型保険(限定告知型保険とも呼ばれます)」があります。
通常の保険への加入が難しい場合でも、こうした保険であれば加入できる可能性があります。
ただし、保険料が割高になったり、保障内容に一部制限があったりするため、注意が必要です。
無選択型保険の特徴
健康状態の告知が不要な「無選択型保険」もあります。
健康状態にかかわらず申し込みができますが、保険料はかなり高額になる傾向があり、保障内容も限定的です。
他のどの保険にも加入が難しい場合の選択肢の一つと考えられます。
事前に準備しておくと良いもの
告知をスムーズに進めるために、手元に準備しておくと良いものがあります。
・健康診断や人間ドックの結果表
・お薬手帳
・過去の入院や手術の際の診療明細書 など
これらの情報があれば、告知書への記入がスムーズになり、間違いを防ぐことにもつながります。
保険相談窓口などの活用
生命保険の加入を検討する際、保険相談窓口などを活用する方法もあります。
保険の専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)は、個々の状況に合わせて保険選びの相談に乗ってくれます。
告知に関する不安や疑問についても説明してくれるので、安心して相談しやすいでしょう。
保険選びに迷っている場合は、専門家の意見を参考にすることも選択肢の一つです。
まとめ
生命保険の告知は、契約を成立させるための重要な手続きであり、正確な情報提供が求められます。
告知範囲は保険商品によって異なりますが、曖昧な表現は避け、具体的かつ詳細に記述しましょう。
告知義務違反は、保険金が支払われない、契約が解除されるといった重大な結果につながるため、細心の注意が必要です。
持病など健康状態に不安がある方向けの保険商品も存在します。
不安な点があれば、ご自身で判断せず保険会社に確認したり、専門家に相談したりして、適切なアドバイスを得ることが大切です。
正確な告知を行うことが、将来の安心を守ることにつながります。