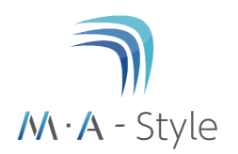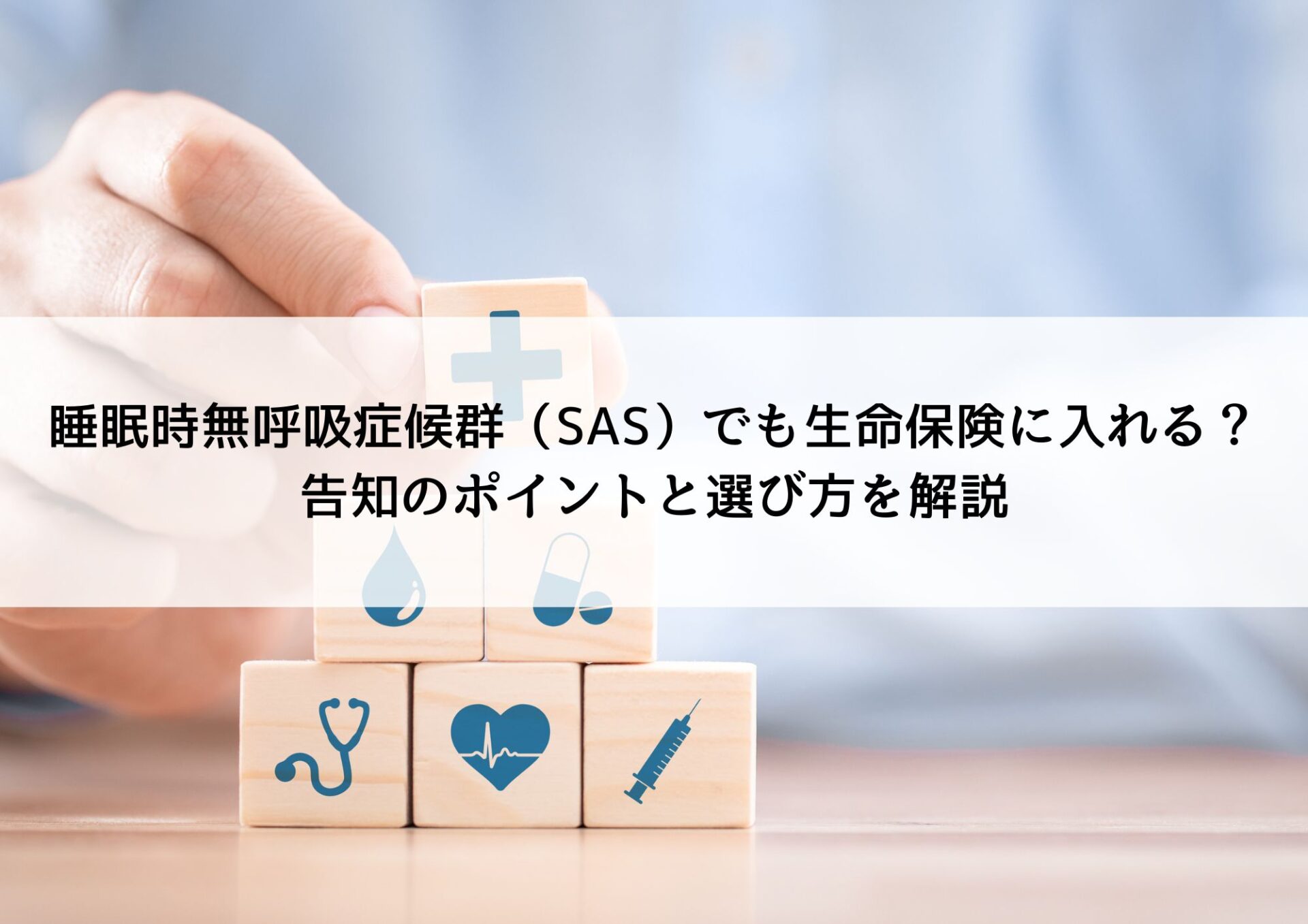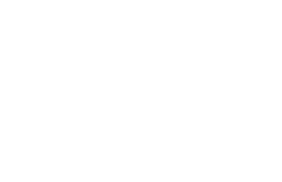夜中に何度も目が覚めたり、日中に強い眠気に襲われたりすることはありませんか。
もしかしたら、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)かもしれません。
SASは、睡眠中に呼吸が止まることを繰り返す病気で、様々な健康リスクを高めることが知られています。
生命保険への加入を検討する際、SASであることは告知事項に該当するため、加入に影響を与えることがあります。
この記事では、SASと生命保険に関する疑問を解消し、保険選びの参考となる情報を提供します。
◻︎睡眠時無呼吸症候群(SAS)と生命保険加入の基本
*SASの告知義務について
生命保険に加入する際は、過去の病歴や現在の健康状態などを保険会社に正しく伝える「告知義務」があります。
SASと診断されている場合は、告知義務の対象となります。
具体的には、SASの診断の有無、重症度(AHI)、合併症の有無、治療内容(CPAP療法など)を正確に申告する必要があります。
万が一、事実と異なる告知をした場合「告知義務違反」となり、いざという時に保険金や給付金が支払われない可能性がありますので検査入院なども含め、正直に申告することが極めて重要です。
*重症度(AHI)と保険加入の関係
SASの重症度は1時間あたりの無呼吸と低呼吸の回数を示す「AHI(無呼吸低呼吸指数)」で判断されます。
保険会社は、このAHIの数値を審査の重要な判断材料の一つとしています。
一般的に軽症の場合は通常の保険に加入できる可能性が高まりますが、中等症や重症の場合は、加入のハードルが上がったり保険料が割増になったり、特定の保障が制限されたりする可能性があります。
*合併症の影響
SASは、高血圧、糖尿病、心疾患、脳血管疾患などの合併症を引き起こすリスクがあるといわれています。
そのため、合併症の有無やその治療状況も保険の加入審査に影響を与えます。
合併症があったとしても、適切な治療によってコントロールされている場合は保険に加入できる可能性が高まります。日頃からの健康管理が大切です。

◻︎ご自身に合った生命保険を検討するために
*保険会社による引受基準の違い
SASに対する引受基準は、保険会社によって異なります。
ある保険会社では加入が難しくても別の保険会社では条件付きで加入できる、といったケースも考えられます。
そのため、最初から一つの保険会社に絞らず複数の保険商品を比較検討することが選択肢を広げることにつながります。
*【補足】引受基準緩和型保険という選択肢
持病がある方向けに、告知項目を少なくして加入しやすくした「引受基準緩和型保険」という種類もあります。
SASの症状や治療状況によっては、こうした保険が選択肢となる場合があります。
ただし、保険料が割高になるなどの注意点もあるため、保障内容とあわせて慎重に検討する必要があります。
*加入審査で考慮される可能性のある点
SASの診断を受けている場合でも、加入審査において以下のような点が考慮されることがあります。
客観的なデータの提出: AHIの数値など、検査結果を正確に伝えること。
適切な治療の継続: CPAP療法などを継続し、症状がコントロールされていること。
健康状態の改善努力: 生活習慣の改善など、健康維持に努めていること。
医師の診断書や健康診断結果などを提出することで、審査がスムーズに進む場合もあります。
*専門家への相談という選択肢
保険選びに迷う場合は、ファイナンシャル・プランナー(FP)や保険代理店などに相談する方法もあります。
相談する際は、AHIの数値、合併症の有無、治療状況などの情報を正確に伝えることで、ご自身の状況に合ったアドバイスを得やすくなるでしょう。

◻︎保険プランの検討と注意点
*ご自身に必要な保障を考える
保険を検討する上で、まずはご自身のニーズを明確にすることが大切です。
万が一の際の死亡保障を重視するのか、病気やケガの際の医療保障を重視するのか、
また、どのくらいの保障額が必要で保険料はいくらまでなら無理なく支払えるのか、などを整理してみましょう。
その上で、複数のプランを比較し、ご自身が納得できるものを選ぶことが重要です。
*治療費と保険給付の関係
SASの治療で入院や手術をした場合、加入している医療保険から給付金を受け取れる可能性があります。
ただし、すべての治療費が保険給付の対象となるわけではありません。
例えば、診断のための検査入院は給付金の支払対象外となるケースもあります。
ご自身の保険契約の内容をよく確認し、給付の範囲を理解しておきましょう。
◻︎まとめ
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の方が生命保険への加入を検討する際は、告知義務を正しく果たすことが大前提となります。
その上で、SASの重症度(AHI)や合併症の有無、治療状況などが総合的に判断されます。
保険会社によって引受基準は異なるため、複数の商品を比較検討することが大切です。
不安な場合は、専門家へ相談することも選択肢の一つです。
正しい知識を持って準備を進めることが、将来の安心につながる重要なステップとなるでしょう。